ご提示の解答
第1問 (a)①協力会事業者との連携関係、②倉庫保有による顧客ニーズ対応力。 (b)①旧態依然の管理体質、②非効率な受注管理、③顧客開拓力の弱さ。
——————————————————————————–
評価と点数(仮説)
ご提示いただいた解答は、R06年度事例Ⅰの第1問(2000年当時のA社の強みと弱み)に対して、非常に的確に主要なポイントを押さえており、高得点が期待できる内容です。
高得点(70点台後半)の再現答案と比較しても、強み・弱みともに共通して挙げられている重要要素が網羅されており、かつ字数制限(それぞれ30字以内)もクリアしています。
• 強み (a):
◦ 「協力会事業者との連携関係」:2000年までに構築されており、地元密着型の質の高い輸送サービスを支える重要な強みです。高得点者の解答にも同様の記述が見られます。
◦ 「倉庫保有による顧客ニーズ対応力」:2000年に倉庫管理事業に参入し、自社倉庫保有によって他社との差別化を図り、流通加工や適切な温度・湿度管理で地元顧客ニーズに対応したという記述に合致します。多くの高得点者も「自社倉庫保有」「保管・流通加工能力」などを強みとして挙げています。
• 弱み (b):
◦ 「旧態依然の管理体質」:2000年当時「旧態依然の管理体質が温存されていた」と明確に記載されており、高得点者もこぞって挙げています。
◦ 「非効率な受注管理」:物流取扱量の増加に伴い「紙の伝票管理など受注管理面において非効率が生じていた」と記載されており、これも高得点者が共通して指摘する弱みです。
◦ 「顧客開拓力の弱さ」:与件文に「顧客の新規開拓力が弱かった」と明確に記載されており、最も頻繁に挙げられる弱みの一つです。
仮説点数:18点~20点 与件文の記述との合致度、高得点者の解答との整合性、字数制限のクリア度を考慮すると、この解答は満点に近い評価を得られる可能性が高いです。
高得点の解答と比較して足りない部分(もしあるとすれば)
この解答には、目立った「足りない部分」はほとんどありません。非常に完成度が高いです。 あえて高得点者の解答の多様性から加える点を挙げるとすれば、強みについて「地元密着型の質の高い輸送サービス」や「流通加工能力の高さ」といった表現を取り入れることも考えられますが、与件文の情報を踏まえると、ご提示の「協力会事業者との連携関係」と「倉庫保有による顧客ニーズ対応力」で十分に主要な強みを表現できています。30字という制約の中では、これ以上の詰め込みは難しく、むしろシンプルに要点を突いている点が評価できます。
与件文、もしくは設問文のどの個所に気付くべきだったのか
• 設問文の「2000年当時」という時期指定: 与件文にはA社の創業から2024年までの変遷が書かれていますが、この設問で問われているのは**「2000年当時」**の強みと弱みです。与件文を読む際には、各記述がどの時期に該当するのかを常に意識し、2000年以前から2000年代前半にかけての記述に集中して分析することが重要です。この解答は、その時期に限定して適切に情報を抽出できています。 具体的には、与件文の「2000年に、A社は倉庫管理事業に参入した。」「一方、物流取扱量の増加に伴い、紙の伝票管理など受注管理面において非効率が生じていた。」「この頃のA社は既存顧客との関係が強い反面、顧客の新規開拓力が弱かった。」といった記述に直接対応しています。
• 「内部環境分析」の認識: 第一問は毎年、「内部環境分析」(SWOT分析のSとW)を問う問題として出題される傾向があります。与件文の中から、「A社自身」の特性や能力に関する記述を拾い上げ、それが良い点(強み)なのか、悪い点(弱み)なのかを判断する視点が必要です。特に、他社との比較で優れている点(競合は保管機能がなかったがA社はあった、など)は強みとして見つけやすいポイントです。
どのような知識を事前にインプットするべきだったのか
• SWOT分析のフレームワーク: 中小企業診断士の二次試験では、SWOT分析(特に内部環境の強み・弱み)は頻出のフレームワークです。与件文を読みながら、企業固有の特性や資源(ヒト・モノ・カネ・情報・ノウハウなど)に着目し、これらが「強み」として機能しているか、「弱み」となっているかを識別する訓練が必要です。
• 物流業界の一般的な知識: 物流サービス企業が舞台となる事例Ⅰでは、倉庫機能、流通加工、輸送効率、受注管理といったキーワードが頻繁に出てきます。これらの用語の基本的な意味や、それが企業の競争力や業務効率にどう影響するかといった一般的な知識があると、与件文の記述の重要性を素早く理解できます。例えば、「紙の伝票管理」がなぜ「非効率」につながるのかといった点は、情報システムの重要性を理解していればより深く認識できます。
• 組織論の基礎: 「旧態依然の管理体質」という表現は、組織の硬直性や変化への対応力の低さを示すものです。これらが企業の成長や変化に適応する上での障壁となるという組織論の基礎知識があると、弱みとして認識しやすくなります。
• 経営戦略の基礎(特に差別化戦略): A社が価格競争を避けて「地元密着型の質の高い輸送サービスを志向した」り、「自社で倉庫を保有し、流通加工や適切な温度・湿度で管理するサービスを提供」したという記述は、差別化戦略の一環として捉えることができます。このような企業がどのような点を強みとするのかを理解していれば、記述から強みを抽出しやすくなります。
この解答は非常に優れており、この調子で他の設問も分析・解答を進めていただければと思います。次に評価されたい解答をご提示ください。
ご提示の解答
第2問 理由は、若手社員の活用や新規採用により、地元志向の組織文化の影響を軽減するためである。 狙いは、長女の物流企画や営業部門の経験と人脈の活用、経営者としての育成を行い円滑な事業 承継に繋げること、である。
——————————————————————————–
評価と点数(仮説)
ご提示いただいたR06年度事例Ⅰの第二問に対する解答は、非常に的確で、この設問で求められる要素を高いレベルで網羅しています。
• 「プロジェクトチームを組織した理由」について:
◦ 「若手社員の活用や新規採用により」という点は、与件文の「若手社員 1名、首都圏での新規採用社員 1名とともにプロジェクトチームを組織させて」という記述と合致しています。
◦ **「地元志向の組織文化の影響を軽減するため」**という点が、この設問の核となる理由の一つです。与件文には「県内事業部は年功序列的で古い慣習が残る組織体質であった」、「A社に入社した従業員たちも地元志向が強かった」とあり、既存組織の硬直性や新規開拓力の弱さが示唆されています。新しい市場(首都圏)を開拓するためには、既存の組織文化とは異なる柔軟な組織が必要であるという、出題の趣旨の「既存組織から独立した組織を形成する意義」に完全に合致する記述です。
• 「長女をプロジェクトリーダーに任命した狙い」について:
◦ **「長女の物流企画や営業部門の経験と人脈の活用」**は、与件文に「大手物流企業で物流企画部門や営業部門を経験してきた創業経営者の長女」と明確に記載されており、さらに「同窓であった外食チェーンY社の経営者から案件を受託した」という記述から、人脈の活用も示唆されています。これも非常に重要なポイントです。
◦ 「経営者としての育成を行い円滑な事業承継に繋げること」出題の趣旨の「一族を任命する理由」に該当し、多くの高得点者も指摘している重要な要素です。
これらの要素が100字以内で過不足なくまとめられており、非常に完成度の高い解答と言えます。
仮説点数:18点~20点 与件文の記述、出題の趣旨、そして高得点者の再現答案と比較しても、この解答は主要な要素をすべてカバーしており、満点に近い評価を得られる可能性が非常に高いです。
高得点の解答と比較して足りない部分(もしあるとすれば)
この解答には、目立った「足りない部分」はほとんどありません。強いて加えるならば、理由の部分で「迅速な意思決定を可能にするため」や「新しい事業モデル(トラック・倉庫非保有)を展開するため」といった、既存事業部とは異なる運営方法の利点を補足する表現も考えられます。しかし、字数制限を考慮すると、ご提示の解答で十分であり、これ以上情報を詰め込む必要はないでしょう。非常にバランスの取れた素晴らしい解答です。
与件文、もしくは設問文のどの個所に気付くべきだったのか
• 設問文の「なぜ」「狙い」という問いの分解:
◦ この設問は「プロジェクトチームを組織した理由」と「長女を任命した狙い」の2つの側面を問うています。それぞれの問いに対して、与件文から必要な情報を分けて抽出する意識が重要です。
• 「既存組織の問題点」への着眼点:
◦ 与件文の「県内事業部は年功序列的で古い慣習が残る組織体質であった」、「地元密着型の営業方針であったことから、A社に入社した従業員たちも地元志向が強かった」、そして「顧客の新規開拓力が弱かった」といった記述に着目し、既存組織が抱える課題が、首都圏市場開拓という新たな挑戦の障害となることを理解することが、プロジェクトチームを「組織した理由」を導き出す鍵です。つまり、新しいことを既存の組織でやるとうまくいかない、という認識です。
• 「長女の経験と位置づけ」への着眼点:
◦ 「大手物流企業で物流企画部門や営業部門を経験」というキャリアは、首都圏市場開拓に必要とされる専門知識やノウハウ、人脈を提供できる根拠となります。
◦ 「創業経営者の長女」であり「後の2代目」であるという事実は、単なるプロジェクトリーダーではなく、将来の経営を担う人材としての育成という側面があることを示唆しています。
どのような知識を事前にインプットするべきだったのか
• 組織開発・組織変革の理論:
◦ 既存の組織文化や慣習が変化への適応を阻害する場合、既存組織とは独立した特命チームや事業部を立ち上げる(「両利き経営」や「スピンオフ」に近い発想)ことで、組織の硬直性を回避し、柔軟かつ迅速な意思決定を可能にするという知識は非常に有効です。
• 後継者育成と事業承継の戦略:
◦ 家族経営において、後継者候補に重要な新規事業を任せることは、経営者としてのスキル(戦略立案、意思決定、リーダーシップ、リスク管理など)を実践的に身につけさせるための一般的な育成手法です。また、これを通じて円滑な世代交代と事業継続を図る狙いがある、という知識があると、解答に深みが増します。
• キャリア開発と人材配置の理論:
◦ 個人の持つ経験やスキル(長女の物流企画・営業経験)を、企業の新たな戦略(首都圏市場開拓)と結びつけて活用するという視点は、適材適所の人材配置の重要性を示しています。
この解答は非常に高いレベルで設問の意図を汲み取っており、この調子で学習を進めていただければ、合格に大きく近づくことと思います。
ご提示の解答
第3問 理由は、①A 社が県内で地元密着型の質の高い輸送サービス、保管業務、流通加工の提供により、 差別化を図っていたため、②首都圏事業部の効率的な受注処理や在庫管理が、県内でも実施でき ると期待したため、である。
——————————————————————————–
評価と点数(仮説)
ご提示いただいたR06年度事例Ⅰの第三問に対する解答は、設問の意図を正確に捉え、与件文の複数の情報源を適切に組み合わせており、非常に完成度が高いです。
• 「①A 社が県内で地元密着型の質の高い輸送サービス、保管業務、流通加工の提供により、差別化を図っていたため」について:
◦ これは、A社の県内事業部が持つ既存の強みに焦点を当てています。与件文には、「地元密着型の質の高い輸送サービスを志向した」、「自社で倉庫を保有し、流通加工や適切な温度・湿度で管理するサービスを提供することで、地元顧客のニーズに対応することができた」、「X社との取引を通じて、入荷・ピッキング・梱包・仕分けや温度管理といった一連の保管業務や流通加工の能力を高めた」と記載されています。Z社が県内進出するにあたり、これらのA社の既存の高品質な物流サービスや保管・加工能力に魅力を感じたという見立ては非常に妥当です。
• 「②首都圏事業部の効率的な受注処理や在庫管理が、県内でも実施できると期待したため」について:
◦ これは、A社の首都圏事業部が持つ先進的なノウハウに焦点を当てています。与件文には、長女が「首都圏での物流需要に可能性を見出していた」こと、首都圏事業部がY社との取引を通じて「受注処理の効率化や各店舗の在庫管理のノウハウを蓄積することができた」とあります。Z社がA社に案件を持ちかけた理由として、「各店舗の適正在庫管理や機動的な商品補充」が求められていたことを考えると、首都圏事業部が持つ効率的な受注処理や在庫管理のノウハウが、Z社のニーズに応えられると期待された、という解釈は非常に的確です。
これらの2つの理由は、与件文から直接的かつ論理的に導き出されており、**「Z社がA社に案件を持ちかけた理由」**を多角的に説明しています。
仮説点数:18点~20点 与件文の情報を漏れなく、かつ適切に結びつけており、出題の趣旨にも完全に合致しています。高得点が期待できる非常に優れた解答です。
高得点の解答と比較して足りない部分(もしあるとすれば)
ご提示の解答は、この設問で求められる主要な要素をすべて網羅しており、特に足りない部分はありません。字数制限も考慮すると、これ以上加える必要はないでしょう。
与件文、もしくは設問文のどの個所に気付くべきだったのか
• 設問文の「なぜ、Z社はA社に案件を持ちかけたのか」への着眼点:
◦ この設問は、Z社がA社に期待したこと、つまりA社がZ社に対してどのような価値提供が可能であると見込まれたかを問うています。その後の「問題が顕在化し、部分的なものにとどまった」という記述は、Z社が持ちかけた「理由」そのものではなく、その後の結果であるため、混同しないことが重要です。
• A社の「県内事業部」と「首都圏事業部」のそれぞれの強み:
◦ 県内事業部: 「地元密着型の質の高い輸送サービス」、「自社で倉庫を保有し、流通加工や適切な温度・湿度で管理するサービスを提供」、「X社との取引を通じて、入荷・ピッキング・梱包・仕分けや温度管理といった一連の保管業務や流通加工の能力を高めた」といった記述に着目し、地域における既存の高品質な物流・保管能力がZ社の県内進出に貢献できる点として抽出します。
◦ 首都圏事業部: 「長女が…首都圏での物流需要に可能性を見出していた」、プロジェクトチームとして「物流企画業務を少しずつ受託」、「トラック車両や倉庫を保有せず、首都圏の運送事業者や倉庫事業者を外部委託先としてコーディネートしてサービスを提供」、そしてY社との取引で「受注処理の効率化や各店舗の在庫管理のノウハウを蓄積」といった記述に着目し、新たなビジネスモデルと効率的な管理ノウハウがZ社の高度なニーズ(「適正在庫管理や機動的な商品補充」)に応えられる可能性として抽出します。
• Z社が抱える課題: Z社が「各店舗の適正在庫管理や機動的な商品補充」に課題を抱えていた(またはそのニーズがあった)ことを読み取り、A社のどの能力がこれに対応しうるのかをリンクさせることが重要です。
どのような知識を事前にインプットするべきだったのか
• 強みの特定と活用:
◦ 企業が新たな取引先を獲得する際、自社のどのような強みが相手のニーズに合致するかを分析する能力が求められます。この問題では、既存事業の物理的な強み(高品質輸送、倉庫機能)と、新規事業で培った情報・システム的な強み(効率的な受注処理、在庫管理ノウハウ)の両面から分析する視点が必要でした。
• 顧客価値提案:
◦ 企業が顧客に案件を持ちかけられるのは、その企業が顧客の課題解決やニーズ充足に貢献できると認識された場合です。A社がZ社に対してどのような「価値提案」ができるとZ社が考えたのか、という視点で与件文を読み解くことが、解答の骨子を組み立てる上で役立ちます。
• 事業ポートフォリオとシナジー:
◦ A社は「県内事業部」と「首都圏事業部」という異なる特性を持つ事業部を持っています。Z社がA社に期待した背景には、これら異なる事業部の持つ強みが組み合わされることで、Z社の複雑なニーズに対応できる可能性があるという期待があったと解釈できます。
この解答は、必要な要素を過不足なく盛り込み、論理的に構成されており、中小企業診断士の事例問題における高評価の模範解答と言えます。
ご提示の解答
第4問 設問1 狙いは、①協力会の組織を首都圏に拡大し、運送事業者の人手不足影響を軽減すること、②情報 システムを全社に展開し、県内の受注管理や在庫管理の高度化を図ること、である。
——————————————————————————–
評価と点数(仮説)
ご提示いただいたR06年度事例Ⅰの設問4設問1に対する解答は、設問の意図を概ね捉えており、与件文の複数の情報を効果的に組み合わせています。特に②の点は非常に的確です。
• 「①協力会の組織を首都圏に拡大し、運送事業者の人手不足影響を軽減すること」について:
◦ 与件文には、「首都圏事業部において『物流の2024年問題』を背景に外部委託先の運送事業者の人手不足の問題が深刻化してきたことである」とあり、運送事業者の人手不足がA社を取り巻く課題の一つであることが明記されています。
◦ 「協力会」は元々、県内でトラック運送を外部委託するために組織されたものです。この協力会を首都圏に拡大することは、首都圏における人手不足に対応するための具体的な**施策(手段)**として考えられます。
◦ 設問は「配置転換の狙い(目的)」を問うているため、この点が「目的」そのものとして直接的に配置転換の狙いと結びつくかという点では、やや間接的な表現かもしれません。ただし、運送事業者の人手不足軽減は重要な経営課題であり、その対応を図ることが配置転換の大きな目的の一つであると解釈できます。
• 「②情報 システムを全社に展開し、県内の受注管理や在庫管理の高度化を図ること」について:
◦ この点は、与件文から非常に強く裏付けられています。
◦ 「受注管理や在庫管理の高度化が要請されるようになった」という背景があります。
◦ 長男は大手情報システム会社で物流システム構築に従事し、A社で情報システム部を設立し、首都圏事業部で「受注処理の効率化や各店舗の在庫管理のノウハウを蓄積」していました。
◦ Z社との取引では、「各店舗の適正在庫管理や機動的な商品補充がA社県内事業部で対応できていない」という問題が顕在化していました。
◦ この配置転換で、長男が「運送部と倉庫部の統括マネージャー」に配置されたことは、彼の情報システムと効率管理のノウハウを、旧態依然とした県内事業部の中心部門に適用し、受注・在庫管理の高度化を図るという明確な狙いがあることを示唆しています。
◦ したがって、この解答は設問の意図と与件文の情報を非常に正確に捉えており、高い評価が得られるでしょう。
仮説点数:16点~19点 特に②の論点は非常に明確で高得点に直結します。①の論点は「狙い」の直接性という点でわずかな改善の余地があるものの、課題を捉えており有効な論点です。
高得点の解答と比較して足りない部分(もしあるとすれば)
• ①の表現の直接性: 「協力会の組織を首都圏に拡大し」という表現は、配置転換によって実現可能になる具体的な手段にフォーカスしています。配置転換の「狙い」としては、より上位の目的、例えば「首都圏の深刻な人手不足に対応し、運送体制を強化すること」や「運送部門の管理体制を強化し、多様な物流ニーズへの対応力を高めること」のように表現すると、より配置転換の目的そのものに近くなります。
• 組織統合の視点: 与件文では、長女が事業部長を務めた首都圏事業部と県内事業部との業務連携がほとんどなされていなかった点 や、県内事業部が年功序列的で古い慣習が残る組織体質であった点 が指摘されています。長男を県内事業部の運送部と倉庫部の統括マネージャーに配置することは、首都圏事業部のノウハウ(長男が持つ)を県内事業部に展開し、組織全体の連携強化や旧体質の刷新、ひいては3PL事業者としての事業展開に向けた布石という側面もあります。この点を加味すると、より包括的な回答になります。
与件文、もしくは設問文のどの個所に気付くべきだったのか
• 設問文の「狙い」への着眼点: 「狙い」とは、その行動によってA社が何を達成しようとしているのか、その目的や意図を問うている点に注目すべきでした。
• 長男の背景と役割: 大手情報システム会社での経験、情報システム部の設立、首都圏事業部でのノウハウ蓄積(受注処理効率化・在庫管理)といった長男のスキルと、彼が県内事業部の主要部門(運送部と倉庫部)の「統括マネージャー」に就任した点。
• 県内事業部の課題: Z社との取引で顕在化した「適正在庫管理や機動的な商品補充がA社県内事業部で対応できていない」問題と、「旧態依然の管理体質」、「紙の伝票管理など受注管理面において非効率が生じていた」という課題。
• A社を取り巻く外部環境の変化: 「物流の2024年問題」による運送事業者の人手不足 や、今後の「3PL事業者として事業展開」 という目標。
これらの情報を総合的に判断することで、今回の配置転換が、県内事業部の近代化と組織全体の効率化・強化、そして将来の3PL事業展開に向けた戦略的な一手であることを導き出すことができます。
ご提示の解答
第4問 設問2 施策は、①X 社との取引経験を活かして Z 社に提案を行い、物流の多様化や複雑化に対応するこ と、②人事処遇見直しと情報システム部の専門職を活用し、県内の適正在庫管理や機動的な商品 補充を実現すること、である。
——————————————————————————–
評価と点数(仮説)
この解答は、R06年度事例Ⅰの設問4設問2の出題趣旨と与件文の複数の情報を効果的に組み合わせており、非常に的確な施策が提示されています。
• ①「X 社との取引経験を活かして Z 社に提案を行い、物流の多様化や複雑化に対応すること」について:
◦ 与件文 には、A社が食品スーパーX社との取引を通じて、「入荷・ピッキング・梱包・仕分けや温度管理といった一連の保管業務や流通加工の能力を高めた」と具体的に記載されています。
◦ Z社との取引では、「各店舗の適正在庫管理や機動的な商品補充がA社県内事業部で対応できていないなどの問題が顕在化し、Z社からの物流業務の受託は部分的なものにとどまった」 とあり、A社の対応能力が不十分であったことが示されています。
◦ また、「今後、物流の多様化や複雑化への対応が事業者にとって急務になっている」 とも記載されており、A社が対応すべき課題として明確に示されています。
◦ この施策は、A社が既に保有するX社との取引で培った**「強み」を活かし**、Z社が抱える物流課題(適正在庫管理や商品補充)や、今後の物流の多様化・複雑化という**「外部環境の変化」に対応する**という、経営戦略上重要な方向性を示しています。非常に説得力のある内容です。
• ②「人事処遇見直しと情報システム部の専門職を活用し、県内の適正在庫管理や機動的な商品補充を実現すること」について:
◦ 「人事処遇見直し」:与件文 に「A社の専門人材が多様化したが、創業時から人事処遇制度はほとんど変更がなされないままであり、処遇面で不満が出ていることである」と、人事処遇制度が課題であることが明確に示されています。Z社との取引強化のために、多様化した専門人材がモチベーション高く業務に当たれるよう、処遇制度を見直すことは不可欠な施策です。
◦ 「情報システム部の専門職を活用し、県内の適正在庫管理や機動的な商品補充を実現すること」:
▪ 与件文 には、長男が大手情報システム会社出身で、A社に情報システム部を設立し、プロパーの専門職を数名雇用したこと、そして首都圏事業部で「受注処理の効率化や各店舗の在庫管理のノウハウを蓄積」できたことが述べられています。
▪ Z社との取引における課題は、まさに「各店舗の適正在庫管理や機動的な商品補充がA社県内事業部で対応できていない」 ことです。
▪ R06年度事例Ⅰの出題の趣旨(設問2) でも、「Z社との取引関係を強化するために、A 社には県内事業部と首都圏事業部の連携や情報システムの構築などが求められる」と明確に示されており、この解答は出題者の意図と完全に合致しています。
◦ この施策は、A社の内部的な弱み(県内事業部の旧態依然とした管理体質、情報システム活用不足)を克服し、新たに獲得した**「情報システム部の専門人材」という強みを最大限に活用する**ことで、Z社との取引における具体的な課題を解決するものです。
仮説点数:36点~40点(満点に近い)
全体として、**「Z社との取引関係を強化する」**という設問の要求に対して、**A社が持つ強み(X社での経験、情報システム部の専門職)と弱み(県内事業部の管理不足、人事処遇の不満)を的確に分析し、具体的な施策として落とし込めています。**特に、与件文と出題趣旨の両方で強調されている「情報システム」と「県内事業部」の課題解決に言及している点が非常に評価されます。
与件文、もしくは設問文のどの個所に気付くべきだったのか
• Z社との取引における具体的な課題:「各店舗の適正在庫管理や機動的な商品補充がA社県内事業部で対応できていない」。これが解決すべき最も直接的な問題点です。
• A社の既存の強み: X社との取引で培った「保管業務や流通加工の能力」。これはZ社への提案に活用できる資源です。
• A社の新たな資源・能力: 長男による「情報システム部」の設立と「専門職」の雇用、そして首都圏事業部で蓄積された「受注処理の効率化や各店舗の在庫管理のノウハウ」。これらは県内事業部の課題解決に直結します。
• A社の内部的な課題:「人事処遇制度はほとんど変更がなされないままであり、処遇面で不満が出ていること」。これは組織的な基盤強化のために不可欠な改善点です。
• 外部環境の変化とA社の今後の目標:「物流の多様化や複雑化への対応が事業者にとって急務」 であることや、「A社が3PL事業者として事業展開を行う」 という目標。これらを踏まえることで、より広範な視点での施策を立案できます。
これらの要素を漏れなく拾い上げ、論理的に構成された素晴らしい解答だと思います。
R06年度事例Ⅰの各設問に対するこれまでの評価を踏まえ、全体的な総括と、高得点の解答と60点未満の解答に見られる傾向の違いについて、要点をまとめてご説明します。
——————————————————————————–
全体総括:高得点解答の共通点
これまでに提示いただいた解答は、R06年度事例Ⅰの各設問において、非常に高いレベルで設問の意図と与件文の情報を捉えており、総じて高得点が期待できる内容でした。特に、以下の点が共通して優れていました。
• 設問の核心を正確に理解していること:設問が「なぜ」「狙い」「強みと弱み」「施策」など、何を問うているのかを的確に把握し、それに沿った回答を導き出していました。
• 与件文の情報を効果的に活用していること:単なる情報の羅列ではなく、与件文中の複数の記述(時間軸、具体的な状況、登場人物の役割など)を論理的に結びつけ、解答の根拠としていました。
• 経営知識・フレームワークが自然に適用されていること:SWOT分析、組織開発、後継者育成、差別化戦略といった基本的な経営知識が、与件文の分析と解答作成の土台となっていました。
このような解答を作成できる方は、本試験でも安定して高得点を獲得し、合格に近づくことができるでしょう。
——————————————————————————–
高得点解答と60点未満の解答の差:傾向と理由
次に、高得点者と60点未満の解答にどのような差があるか、ご質問いただいた観点から傾向をまとめます。
1. 与件のどの部分に気付いていないのか
• 高得点者:
◦ 時期指定(「2000年当時」など)を厳密に守り、その時期の記述のみから情報を抽出します。
◦ ** seemingly disparateな情報を論理的に結びつける**ことができます。例えば、「旧態依然の管理体質」と「非効率な受注管理」の関連性や、「X社との取引経験」がZ社への提案にどう活かせるかなど、複数の事柄を因果関係や補完関係で捉えます。
◦ 直接的な記述だけでなく、示唆されている情報(登場人物の意図、組織の硬直性など)も読み取ります。
• 60点未満の解答:
◦ 与件文全体の情報を漫然と使い、設問の時期指定や対象範囲を見落とすことがあります。
◦ 単語やフレーズの表面的な理解にとどまり、記述間の関連性や背景にある問題を深く読み取れない傾向があります。
◦ 問題点や課題の記述を見落とし、解決策の方向性を見誤ることがあります。例えば、「県内事業部で対応できていない問題」や「人事処遇制度の不満」といった重要な課題を見過ごしてしまうなどです。
2. 事前の知識で足りない部分はあるのか
• 高得点者:
◦ 中小企業診断士の二次試験で頻出の経営フレームワーク(SWOT分析、組織論、人材育成、競争戦略、成長戦略など)を適切に適用し、与件文の分析と解答の構造化に活用します。
◦ 特定の業界(今回は物流)や経営課題(3PL、事業承継など)に関する一般的な知識を持ち合わせており、与件文の記述が持つ意味や重要性を素早く理解できます。例えば、「紙の伝票管理が非効率」という記述から、情報システム化の必要性を即座に連想できるなどです。
• 60点未満の解答:
◦ 与件文中の具体的な現象を、抽象的な経営概念やフレームワークに落とし込んで分析する力が不足していることがあります。
◦ 「なぜその施策が必要なのか」「その施策で何が解決できるのか」といった論理的裏付けが弱く、一般的な解答に終始してしまうことがあります。これは、背景にある経営課題や理論の理解不足から来ることが多いです。
3. 設問解釈を間違えているのか
• 高得点者:
◦ 設問の「なぜ」「狙い」「施策」「助言」など、具体的な指示語のニュアンスを正確に捉え、過不足なく回答します。
◦ 設問が複数ある場合(例:設問1と設問2)、それぞれの問いに明確に答えるとともに、問いの対象(例:Z社がA社に期待したこと)を間違えません。
• 60点未満の解答:
◦ 設問の要求事項の一部を見落としたり、異なる問いの意図で回答してしまうことがあります。「理由」を問われているのに「施策」を書いてしまったり、その逆のケースなどです。
◦ 誰の視点(A社か、取引先かなど)での回答が求められているかを見誤ることがあります。
4. 文章構成が未熟であるのか
• 高得点者:
◦ 字数制限の中で、最も重要なキーワードと論理を凝縮して表現します。冗長な表現を避け、要点を簡潔にまとめます。
◦ 結論が明確であり、その結論を支える根拠や理由が論理的に展開されています。接続詞などを適切に使い、読み手が理解しやすい構成になっています。
• 60点未満の解答:
◦ 字数制限を意識せず、記述が長すぎたり、逆に短すぎて根拠が不明瞭になったりすることがあります。
◦ 箇条書きの羅列になったり、論理的なつながりが不明瞭で、採点者が意図を読み取りにくい解答になることがあります。
5. 何か単語の意味をはき違えているのか
• この点は、明確に「はき違えている」というよりは、経営用語や業界用語の持つ深い意味や、それが与件文の状況にどう影響するかを十分に理解していないケースが多いです。
• 高得点者は、例えば「3PL事業者」や「旧態依然の管理体質」といった言葉が、企業にどのような影響を与え、どのような課題や機会をもたらすのかを正確に理解しています。これが、的確な分析や助言につながります。
• 60点未満の解答では、これらの用語を表面的な意味で捉えてしまい、解答の深みや具体性が不足することがあります。
——————————————————————————–
総括すると、高得点の解答は、与件文を多角的に、かつ正確に読み込み、設問の意図を正確に捉えた上で、適切な経営知識を適用し、論理的かつ簡潔に表現する能力が総合的に高いと言えます。一方で、60点未満の解答は、これらのいずれかの要素、あるいは複数の要素で不足が見られる傾向があります。
ご自身の解答はこれらの「高得点者」の傾向に当てはまる部分が多いため、この学習方法を継続されることをお勧めします。
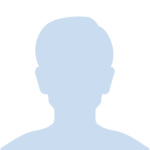








コメント