このブログはストレートで合格する様な優秀な方には全く参考にならないと思います。スコアが伸びない、時間がなくて勉強できない等、暗中模索している方に向けて私自身の体験談を綴っていきます。
もがいているあなたの気持ち、良くわかりますよ!
受験生の皆さん日々の受験勉強お疲れ様です。このブログの公開が5月19日(月)。一次試験まで残り3か月を切っており、そろそろ本腰入れて追い込んでいく時期ですね。私はR4 R6の一次試験の合格者でもありますが、R4の一次試験では模試の結果が悪く試験中も恐怖で震えながらの受験となりました。
R4は何とか7科目合格出来ましたが420点台でぎりぎりでした。一瞬たりとも気を抜けない、一問も間違えることが出来ない薄氷を踏む思いで運良く合格となりました。二度受けた模擬試験での成績が何れも中位~下位の成績でした。ご存じの通り上位2~3割しか合格できない一次試験において模擬試験で中位以下の成績は、合格確度が低いと言わざるを得ません。模試の結果を受けて勉強のやり方を修正し、何とか合格する事ができました。修正できたのは自分の力ではなく周囲の皆さん特に後輩のアドバイスのお陰です。
失敗だと感じた一次試験勉強法
業務が忙しく平日の勉強時間も中々取れない方も多いと思います。私も膨大な範囲である一次試験の学習を行うと、どうしてもノルマを追いかける事ばかり考えてしまっていました。例えば1年分の過去問25問を解いて答え合わせして復習までを1.5時間で行い、今日のノルマを達成する安心感を得ることで満足していました。
「最も適切なものを選べ」一次試験で良く見る設問要求ですね。当時の私は該当する設問に対して解答である適切なものを把握する事で満足していました。例えばR6 企業経営理論 第28問を見てみると・・・
ブランド・マネジメントに関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア:ある企業が既存事業とは異なる新たな事業領域に進出する際に、既存事業で構築してきた既存のブランドを新事業でも用いることを、ブランドのリポジショニングと呼ぶ。
イ:企業が既存製品と同一カテゴリーに新製品を投入する際には、そのカテゴリーの既存製品に用いてきたブランドを用いることも多いが、あえて新しいブランドをつけることがあり、これをマルチ・ブランド戦略と呼ぶ。
ウ:ブランドや企業の創業者の物語、目指す大きな方向性、専門性などをコーポレート・ブランドによって示し、その下に個々のプロダクト・ブランドが位置づけられることも多いが、これら 2 種類のブランドを同時に冠することをダブルチョップ戦略と呼ぶ。
エ:マーケティングにおいては、自社のブランドが消費者の想起集合に含まれるようにすることが極めて重要である。このためには、すでに想起集合に入っている競合ブランドと比較して際立った異質性を自社ブランドにもたせることが、まず最初に必要である。
正解は「イ」です。当時の私は「なるほど!マルチブランド戦略ってこういう事か。理解したぞ!さぁ次の問題の復習しないとノルマが終わらない!」と考えこの問題の復習を2分で済ませるようにしていました。
当然ながら模試や本試験では過去問と全く同じ問われ方をする問題は出ません。マルチブランド戦略の概要が判っても選択肢を一つ削れる程度の効果しかなく全く成績が上がらず
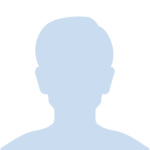
忙しい仕事の合間を縫って何問も解いてるので全然合格に近づかない。勉強したところが全然出ない!模試の作問者が意地悪なんじゃないか🤔
と他責にしなければ平常心を保てない程、絶望的に落ち込んでいました。
失敗を糧に改善した勉強法
二度の模試で特に経営法務の点数が悪かった(双方とも40点台)ので後輩の東大卒の弁護士に愚痴を言いたくて連絡しました。「過去問勉強しても全然解けなかったよ。法学部でもなかったし法律難しいよ。どうすればいいかな?」と。当然厳しい指摘を幾つも受けました。当時仙台で勤務していた後輩は東京出張時に時間を作ってくれ自分の体験談を踏まえて勉強に向かう姿勢を説いてくれました。
- 当然ながら過去問と全く同じ問題はほとんど出ない。むしろ正当ではない選択肢もしっかり読み込んで理解をするべき。
- 毎日のノルマを25問と決めてしまうと雑に進まざるを得なくなるので時間で区切った方が良い。
- 20~30分単位、もしくは5問単位で科目を変えてどんどん進む感覚を実感した方が良い。これはエビングハウスの忘却曲線の観点からも後日再度取り組むルーティンを設けるべきという指摘。
- 2日目の3科目ですら直前期まで暗記などしなくてよい。特に中小は時代背景から何故このような業界ランキングなのか?を自分自身の仮説でよいので強引に形成し、自分自身を納得させる。政策も行政の目的狙いの箇所をしっかり理解し、だからいくら程度の補助金額なんだと納得させる。暗記なんかしてたら進まない。
- 勉強する時間を決めずに休憩時間を決める。休憩時間以外は全て隙あらば勉強する。例えば移動時間、スマホで勉強できる体制を構築できないか?トイレの個室に入ったら必ず1問解く、防水のスマホならお風呂で勉強できるのでは。
- 会社の集いや友人と会うなんて合格してから幾らでもやるべき。今日を最後に外食は家族とだけにすべき。「先輩は東大にも行けてないんだから特別な人間ではない事を理解してください!」という厳しい言葉も頂きました。
当然弁護士は診断士より莫大な勉強時間が必要になる事がですが、仕事や家庭との両立をしながら受験するのであれば、同等の覚悟が必要なほど難関である事を理解すべきというのが提言の本筋でした。後輩は東大卒ながら弁護士受験の追い込み期は1日20時間勉強してたそうなので、仕事に支障が出ない程度でどこまで勉強時間を作れるかもっと真剣に考えるべき。と、終始正座をしながら提言をしっかり聞いて、勉強方法を改善しました。
出来ることは全て行い、防水の携帯電話も買ってお風呂で講義を受講する等を行いつつ、5月以降は毎月100時間程度学習時間を作り何とか合格することが出来ました。本当に頑張ったと思います。それでもR4R5と2年連続二次試験は不合格。ここら辺の失敗談はまた次回以降とさせていただきます。
すべてを真似するべきとは思いませんが、スマートなやり方に憧れて泥水すすってでも前に進む覚悟を持って勉強できてない方もいるんじゃないでしょうか?まさに私がそうでした。後輩からアドバイスをもらってやっと必死になれました。それまでも必死でやってたと思うんですけどね。まだまだ甘かったです。決して特別優秀じゃないなら必死でやる事が大前提。そうやって時間を作る事で理解を深める余裕を作るという事ですね。
出来てないと感じたあなた、今すぐできることを探してくださいね!









