こんちには、カズです。
今回は、私の考える、二次試験で求められる『国語力』について、書かせていただきます。
二次試験は国語の試験か?
中小企業診断士の二次試験に関連して、たまに話題にあがることがあります。
「二次試験は国語の試験だ!」
「国語の試験じゃない!」
意外と2つに意見が割れるような気がします。
その理由を考えてみると、国語の試験で求められること≒『国語力』とは何か、人によって認識が少しずつ異なるために、意見が割れてしまっているんじゃないかな~と思います。
そもそも、国語力とは?
私自身、学生時代から国語は苦手で、試験で何を求められているのか良く分かっていませんでした。
(高校時代、模試で偏差値20台をたたき出したことも…)
そんな私の、国語に対する印象がガラッと変えたのが、ドラマや漫画の『ドラゴン桜』でした。
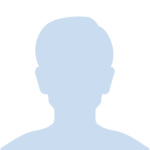
国語は科学です!
科学である以上、合理的、論理的に解析し、帰結を導き出すのです
(ドラゴン桜より引用)
最初は、何言っているんだこいつ…?と思いましたが、非常に納得感があり、理系科目以外はからっきしだった私でも、国語も面白いかも、と思えるようになりました。
(できればもう少し早く、学生時代にこの考えに出会いたかった…)
ドラゴン桜を題材に、非常に読みやすい記事がありましたので、ぜひそちらを参照ください。
『ドラゴン桜』太宰府治先生が教える、東大合格のカギ「読解力」を鍛える方法(モーニング編集部) | 現代ビジネス | 講談社
後々調べてみると、この考え方は、ふくしま式と呼ばれる国語学習メソッドに関係しているようでした。
文章の構造化を把握・整理することが非常に重要であるとされていて、ふくしま式の生みの親である福嶋隆史氏によると、文章構造化に必要な国語力≒論理的思考力とは、以下の3つであると言われています。
・ 言いかえる力 (同等関係を整理する力)
・ くらべる力 (対比関係を整理する力)
・ たどる力 (因果関係を整理する力)
おそらく、国語の試験ではないという方の多くは、診断士としての専門知識(経営や運営管理など)も必要になり、それは国語力の範囲外という意見なんだと思います。
しかし、専門知識があるからこそ二次試験の問題で「言いかえる/くらべる/たどる」ができると考えることもできますよね。そうすると広い意味では、二次試験≒国語の試験 と捉えても良いのかな~と、個人的には思います。
二次試験で役立つフレームワーク
二次試験においては、80分という限られた時間で、かなりの分量の与件文を読み、文章を構造化を整理・把握することが求められます。余程の国語力がない限りは、そう簡単にはいかないと思います。
基礎的な国語力を補うためには、「フレームワーク」をいかに効果的に活用するかが重要だと思います。
(そもそも、適切なフレームワークを選ぶ力というのも国語力に含まれるかもですが)
私なりに、関係しそうな3つの力に分類して、役に立ったと思う主なフレームワークをご紹介します。
言いかえる力 : 同等関係を整理する力
診断士二次試験においては、多面的に要素を盛り込んで解答することで、失点のリスクを最小限に抑えるような工夫をされる方が多いと思いますが、その際に重要になる力かと思います。
サチノヒモケブカイネコ
事例Ⅰで良く問われる要素の頭文字をとったもので、解答要素の抜けもれチェックに使いました。
事例Ⅰは苦手で、書くべき要素を見つけるのが苦手だったので、とても助けられました。
(採用、賃金、能力開発、評価、モラール、権限移譲、部門、階層、ネットワーク、コミュニケーション)
4P
主に事例Ⅱで、競合と比較した自社の強み/弱みを整理するうえで役立ちました。
QCD
主に事例Ⅲで、競合と比較した自社の強み/弱みを整理するうえで役立ちました。
4M
主に事例Ⅲにおいて、強みの源泉や、問題点を洗い出す際に役立ちました。
QCDと比べると具体的な情報になるので、4Mで整理した情報は課題に直接つなげやすかった気がします。
ダナドコ
助言の設問等で、この順番で要素を並べると解答が書きやすいというもの。
(誰に、何を、どうやって、効果)
ちなみに、サチノヒ…とダナドコは、診断士試験固有のフレームだと思います。
くらべる力 : 対比関係を整理する力
3C
診断士二次試験で何かを比較するうえで、3Cは必須ではないでしょうか。
例:競合と自社を比べる、顧客ニーズと自社を比べる
(設問によっては、3Cの他に、時系列(過去と現在など)で対比関係をとることもあるかも。)
たどる力 : 因果関係を整理する力
原因と結果(因果関係)を正しく整理する力、初歩の初歩で超シンプルですが、与件文を読むときも解答を書くときも、非常に重要だと思います。
GISOV
G=Goal(目標)、 I=Isue(課題) S=Solution(解決策)、 O=Operation(実行計画) V=Value(付加価値)の頭文字をとったもの。野村総研で、提案の基本の型として活用されているフレームワークです。
二次試験では、とくにG、I、S、のあたりを意識すると、与件の情報整理がしやすくなったり、助言/提案を求められる設問では解答が書きやすくなるように思います。
また、GとIの間にP(問題)を入れて考えると、より詳しく情報整理できると思います。
以上、気になるものがあれば、ぜひ使ってみてください。
いずれも有名なものですので、調べればもっと詳しい説明が簡単に得られると思います。
国語力のトレーニング方法
国語力向上には、3つの力を組み合わせて適切な整理軸を設定し、文章を構造化する訓練が重要と思います。
事例/設問ごとにいかに適切な整理軸を選択するかで、解答の質もスピードも大きく変わってきますので、試験突破のカギになるように思います。
・ 読むとき ⇒ 情報を構造的に考えて、文章の正しい理解をすばやくできるように!
・ 書くとき ⇒ 文章を構造化して、短文で伝わりやすい文章に!
読む力については、良質な文章に多く触れることで鍛えられると思います。私の場合、以前はほとんど本を読みませんでしたが、仕事で本を使って調べものをする機会が増え、少しずつですが鍛えられました。
具体的には、世間で良著と言われている本を読むことが無難な方法のように思います。
書く力については、実際に文章を書くことと、人に添削してもらうことで鍛えられると思います。私の場合、仕事で資料作成をしている際に、上司・先輩から詰められてアドバイスいただき鍛えられました。
過去問演習はもちろん、100字訓練や春秋要約なども有効と思いますが、注意点として、自分で添削することは難しいです。第三者に見てもらったり生成AIを活用して、添削までもセットで行うと効果が高まると思います。
国語力を伸ばしたい!という方、ぜひ参考にしてみてください。
おすすめ書籍紹介
『「本当の国語力」が驚くほど伸びる本(福嶋隆史)』
冒頭でご紹介した、ふくしま式の国語学習について詳しく説明されています。小中学生のお子さんがいらっしゃれば、お子さんと一緒に読んでみるのも良いと思います。
『最強の「仕事の型」(村井庸介)』
野村総研出身の筆者が、あらゆるビジネスパーソンに役立つ仕事の型として「GISOV」を詳しく説明しています。試験はもちろん、今後の診断士実務においても役立つ場面が多そうだと感じています。









